
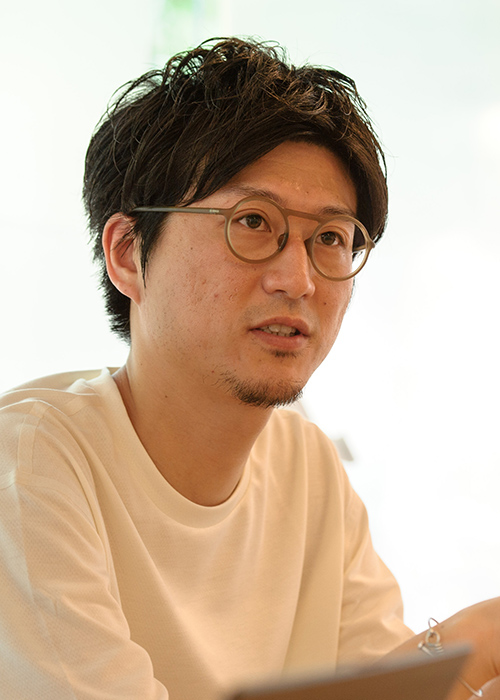
テクノロジーを
自然なものとして
捉えられる空間を
――お2人はAFFECTIVE DESIGNという考え方を伝えるために、リアルな場所としてAFFECTIVE DESIGN STUDIOをつくられました。今回のリニューアルのお話を伺う前に、そもそもの立ち上げの経緯を教えていただけますか?
田中:私たちは2013年ごろから、お客様と、「ゼロベースで新事業やサービスを一緒に考えましょう」という試みを進めてきました。ところが、実際にはじめてみるとお互いを理解するためのコミュニケーションにとにかく時間がかかるということがわかりました。そこで、お客様の考えをまとめていくデザインではなく、自らの思想やビジョンを投げかけお客様の想いと掛け合わせることで、スピード感を保ちつつ、そこから生まれる共感をベースに独自の価値をデザインする場所をつくろうと考えました。そして2018年の春、TAKT PROJECTさんにご相談してAFFECTIVE DESIGN STUDIOを立ち上げました。
――スピード感をもってプロジェクトを進めるために、まずはAFFECTIVE DESIGN PROJECTメンバーのみなさん自身の想いを伝える場所が必要だった、と。
田中:そうですね。この場所は、不特定多数の方々が集まっていわゆるオープンイノベーションを起こすような場所ではなく、セミクローズドな環境にとどめています。これは、文脈をもたない人の偶発的な出会いから何かが起こるのを待つのではなく、「共感」で「共感」が繋がっていくような環境にしたいと思ったからです。
そこでTAKT PROJECTさんには、「あまりデジタルを前面に出したものにはしたくない。もっと人をベースにして、“見えないところで自然にデジタルが存在している”というAFFECTIVE DESIGNの思想が伝わる場所にしたい」とお伝えしました。

――この場所そのものがAFFECTIVE DESIGNの考え方を体現したものになっているのですね。
田中:来ていただければ、私たちがどんな未来を描いているのか、どういう社会をつくろうとしているのかが、ロジックだけではなく「感覚」で伝わるような場所にしたいと考えていたんです。「感覚」で伝えるために、リアルな場があるということはとても重要でした。やはり、自分たちがプレゼンしにいくのと、この場所にきて体感していただくのとでは、伝わり方が大きく違います。
――では、その想いを受けて、TAKT PROJECTのみなさんは、オープン当初の「AFFECTIVE DESIGN STUDIO」にどのような工夫をしていったのでしょう?
吉泉:通常、テクノロジードリブンな領域では、いかにそのテクノロジーがすごいかという伝え方を目指すことが多いですが、田中さんは当時から「人を中心に据えたい」「感じるデザインにしたい」と言われていました。そこで「テクノロジーを自然なものとして捉えられる空間を目指しましょう」とお話をしたのを覚えています。
そのために用意したのが、アイコンとして使用し続けている、白いマネキンです。デジタルの表現を従来とは違う形で感じていただくために、まずは「人がいる風景」を用意して、デジタルが生活の中で自然に作用する様子を伝えたいと思ったんです。人の生活そのものを見せることで、テクノロジーが毎日にどう溶け込んでいけるのかを伝えられるのではないかと考えました。
田中:そうご提案いただいて、何体ものマネキンをすべて「1人の人間のさまざまな瞬間を切り取ったもの」と考えると意味のある見せ方ができると感じました。通常、どんなサービスでも業界のカテゴリーが違えば別ものとされますが、使う「人」を中心に考えると、すべてのサービスは繋がっているほうが自然です。
プロジェクトの立ち上げ当初にはキーグラフィックも用意したのですが、それは透明な肉体と生身の人間が境目なく繋がっているものにしました。これは、「デジタルな要素がそれと気づかれずに人々に接触している、目に見えないけれども人を支えている」という「AFFECTIVE DESIGN」の理想形を表現しています。同時に、床には人の行為は繋がり波及して広がっていく様子をたとえた波紋を用意していただきました。

(提供:AFFECTIVE DESIGN PROJECT)

「日常に溶け込み、
持続するものになるか」が重要
――「見えないものをデザインする」という考え方は、AFFECTIVE DESIGNにとって大事な要素なのでしょうか?
田中:AFFECTIVE DESIGNのポイントは、大量生産のプロダクトをつくって、それを広め「人々がそれに合わせて使っていく」という時代から、情報やサービス自体がそれぞれの人間を理解してアプローチできるようになりつつある今、情報との接点が変わってくるのではないか、というところにあります。より時代が進めば、情報をスマートフォンなどのディスプレイをとおして得るだけではなく、人間の多様な感覚を使った、マルチモーダルなインターフェイスが増えてくるはずです。そのときの新しい情報の感じ方を、色んな生活のシーンで表現すれば、AFFECTIVE DESIGNという考え方を伝えられるだろうと思ったんです。
吉泉:僕自身もデザイナーとして仕事をしていくなかで、共感できる部分が多いです。テクノロジーは、「価値が数値で表せる」「できなかったことができるようになる」など、明快な結果で人を説得できる「強い」ものだと思います。一方、AFFECTIVE DESIGNにとって重要な「(自然な)感覚」は、それに比べて、弱いものだと言えます。
でも実は人の生活は、数値で表せないような弱い感覚で成り立っていることがほとんどですよね。その対立/乖離が大きくあるなかで、「弱くても大切なもの=人の感覚」の視点からテクノロジーをドライブしていくことは、とても大切なことだと感じます。つまり、テクノロジーを否定するわけではなく、いい接し方を模索していく、と言いますか。
田中:テクノロジーは、放っておいても必ず進化していくものだとも思うのですが、だからこそ、人を中心に捉えて、心地よく感じられる状態で社会に実装されるべきです。そういった視点で見ると、まだ独りよがりのデジタルサービスが生活の中にあふれている。
たとえば、どんなにすごい新技術も「誰が求めているのか」を考えられていなければ、うまく世の中に普及していくことはありません。その技術を受け入れる社会や、社会を形作る人々の考えこそが大切です。そして、プロジェクトを進めていくなかでもうひとつ大切なことに気づきました。それが「日常に溶け込み、持続するものになるか」。つまり、長期的な視点で思考すること。その二軸を兼ね備えていることが、重要だと思います。

AFFECTIVE DESIGNとは
「デジタルなエイジング」
――今年8月に「AFFECTIVE DESIGN STUDIO」をリニューアルされましたが、そのあたりの考え方が反映されているのでしょうか?
田中:そうですね。「日常に溶け込み、持続するものになるか」という視点はリニューアル前の「AFFECTIVE DESIGN STUDIO」では伝わらないと気づき、今回の改装を決めました。
吉泉:僕は田中さんとSNSでも繋がっているのですが、田中さんはテクノロジー領域の仕事をされていると同時に、趣味としてていねいに暮らしの魅力を伝えるイベントを開催されている。AFFECTIVE DESIGNではその2つを同時にやられているのではないか、と感じたんです。ていねいに暮らすということは、「ものをていねいに使う/長くものを共有して使う」ことに繋がっていきます。つまり、新品がベストなのではないという考え方です。新品は長い時間をかけて家族のもの、自分のものになっていきます。
そう考えると、データの蓄積によってその人によりフィットしたサービスになっていくことは、「ひとつのものを長く大切につかう」「日々をていねいに暮らす」ということと、ほとんど同じことだと思うんです。ですからスタジオのリニューアルにあたって、AFFECTIVE DESIGNはある意味で「デジタルなエイジングなんじゃないか」と、まずお話ししました。
田中:吉泉さんにお話いただいたように、僕はこういった仕事をしながらも、実はアナログをこよなく愛する人間なんです。だからこそ、日常の暮らしと、デジタルな領域でのできごとの間に、大きな温度差を感じることがあるんです。そして、大きなギャップがあるうちは、まだまだデジタルなサービスを浸透させることは難しいと感じています。
日常の暮らしとデジタルな世界が境目なくつながったとき、初めてテクノロジーはその人にとっての「大切なもの」に変わっていく気がしています。ですから、デジタルな技術をつかって驚くような感動体験をつくるだけではなく、自然に存在しているものにしたい、と考えているんです。



――なるほど。その考え方をリアルな場所にどのように落とし込んでいったのでしょう?
吉泉:「人」「デジタルなもの」「アナログなもの」の3つが共存するシーンを用意しようと考えました。たとえば、「TRAVEL」の項目ではマネキンがスーツケースを持っていて、その周りに見えないデジタルなものが溶け込む様子が表現されています。これはアナログなものと同様に、デジタルなものも自分に対して、時間とともになじんでいくという意味で、2つの要素を等価なものとして扱いたいという想いから生まれたアイデアでした。
田中:また、すべてのマネキンで表現されているひとりの人間の様々な場面が重なる地点に、「その人の真の姿がある」とも感じていて、展示ではその要素も表現しています。
こういう場所をつくるまでは、この考え方をお客様に評価いただけるのか分からない状態でした。けれども、実際にこの場所でお話をしてみると、強く共感していただける方が、非常に多くいらっしゃいました。また、同時にご来訪いただけるお客様が、自らのお客様のことを真意に捉えなおそうと考えているということも分かりました。みなさんの反応からも、我々の考え方が直感的に伝わるスペースになっていると感じています。
――まさに、「AFFECTIVE DESIGN STUDIO」を通して共感が連鎖していったのですね。
吉泉:それはきっと最初に「AFFECTIVE DESIGNで実現したのはどんなことなのか」というお話をしっかりとして、以降も会話を繰り返したことが、大きかったんじゃないかと感じます。
田中:そうですね。自分たち自身も、あいまいなままにしていた部分がクリアになっていく実感がありました。相談しながら、次第に「こういうことを伝えるべきですね」ということが、とても明確になっていって、一緒に考え方を深め合えるような感覚だったと思います。

「自分たちは
何をやっていくのか」
という在り方そのものを
デザインする
――こういった取り組みは、社会にとってどんな意味があると思われますか?
吉泉:こうしたことを、大企業のデザイン部門である田中さんたちが手がけられているということにも、大きな意味があるんじゃないかと感じます。これまで、いわゆるインハウスのデザイナーの仕事は、プロダクトを世に出す最後のタイミングでどう魅力的にするか、という部分を担っていたと思います。でも本来デザインは、「どんなものをつくるのか」という段階から関わる方が、効果を発揮すると思うんです。
つまり、田中さんたちの活動は、「製品をどうデザインするか」ではなく、「自分たちは何をやっていくのか」という会社の在り方そのものをデザインすることとほぼ同義です。そのことに、1人のデザイナーとして希望を感じます。
田中:世界的にも「well-being(=人々や社会にとって良好な状態を指す言葉)」という言葉が注目されるようになった今、「在り方」をどうデザインするのかが、これからの課題になると感じています。
「人々が満たされた状態というのは、どんな状態か?」と考えると、実は求められるのは機能性や効率性だけじゃない、人の心を支えるような存在だと思うんですね。これからの時代、デジタルテクノロジーは否応なしに社会や生活に浸透し、その流れは加速していきます。だからこそ、AFFECTIVE DESIGNのような「在り方」を大切にしながら、デジタルサービスが自然に社会に浸透していけばいいなと考えています。
(取材・文:杉山仁、撮影:平郡 政宏)

