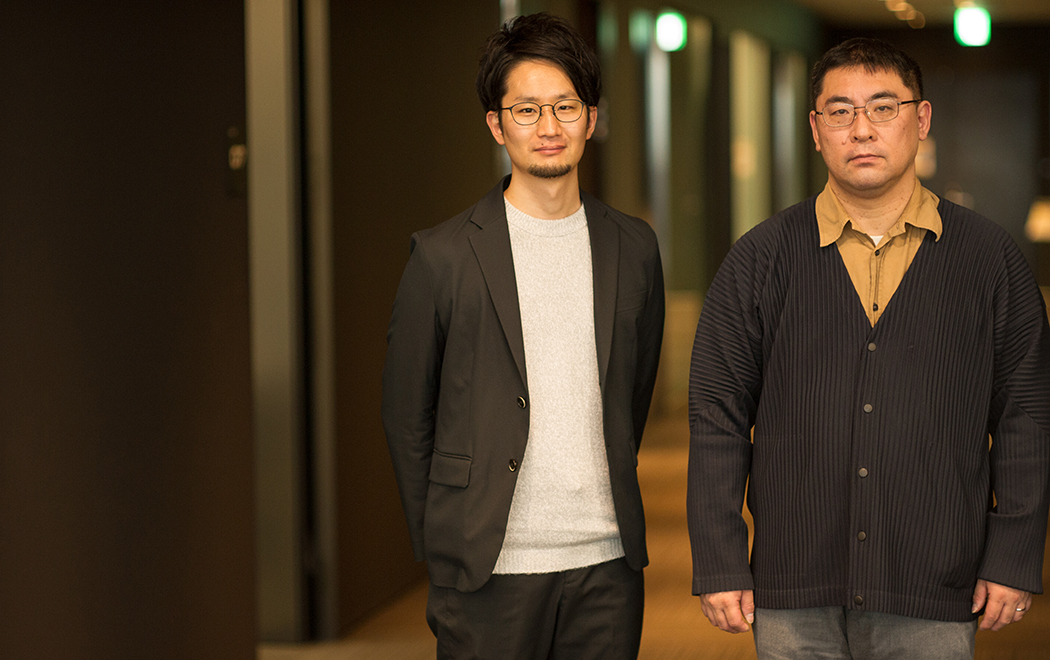ゲームデザインは
“サイエンス”の時代へ
鈴木:我々は、これからテクノロジーが自然に人に寄り添うAffective(情緒的)な社会がやってくると考えています。そのとき、可能になるのが「体験のパーソナライズ」の実現です。これまで、私たちはデータを活用してサービスデザインに取り組んできました。
三宅さんは、ゲームの世界のなかでパーソナライズされた体験を目指してAIを開発されています。特に、三宅さんが開発されている「メタAI」や「キャラクターAI」といったゲームAI同士の関係は、リアルな社会のテクノロジーと人間との関係にも応用できるものがあると感じています。
本日は、ゲームとリアルにおける「体験のパーソナライズ」をテーマにお話を伺いたいと考えています。
三宅:よろしくお願いいたします。
鈴木:まずはゲームデザインの現在について教えてください。PlayStation 4やNintendo Switchといった家庭用ゲーム機に加え、スマートフォン向けにリリースされるソーシャルゲームなど、近年のゲーム市場は非常に多様化が進んでいるように感じます。ゲーム開発の現場は、どのような変化がありますか。
三宅:少し前までのゲーム開発は“直感”がゲームのコンセプトとして大きな役割を占めていました。特に日本では、理詰めでゲームをデザインするよりは、ゲーム開発者のもとに天からアイデアのようなものが降りてきて、それを開発し、発売後にヒットしたり外れたり……といったことが多かったんです。
特に、日本の開発者は世界から見ても、新しいゲームデザインを発信し続け、海外を驚かせてきました。ところが、そのころは「ヒット」の再現性も低く、検証の手段もありませんでした。最近になってようやく、プレイ中の “データ”を使って、ゲームデザインの「ヒット」をサイエンスできるようになりました。

鈴木:「ゲームデザインをサイエンスする」とは、どういうことですか?
三宅:はい。もう少し前段の変遷を詳しくお話すると、2010年代にはゲーム開発のプラットフォームであるゲームエンジンのシェア争いがありました。それが落ち着いた頃、いかにデータ収集を行うかというレイヤーが加わり、サービス向上やチーティング(不正行為)対策のため、ゲームエンジンを通じたユーザーデータの取得が開始されました。あくまで匿名のデータで、統計的な指標を見出すことが目標です。
たとえば、ゲームをプレイしてくれた人の中で何割が最後までクリアしているか、などです。また、取得したプレイデータを機械学習と結びつけるようなトレンドも起こりました。例えばe-Sportsなどでは公平性を保つために、チーティング(不正行為)をしたユーザーをAIが見つけてきてアカウントをBAN(追放)できるようなしくみも生まれつつあります。
かつては、人間が数人、毎日、画面に張り付いていたところから、人工知能が監視しつつあります。また、ソーシャルゲームでは、ゲームディレクターの隣にデータサイエンティストがいる、というゲーム開発会社も出てきています。
鈴木:ユーザーがプレイしたデータが、リリース後のゲームに反映され、ゲームの内容が変わるようなこともあるのでしょうか。
三宅:はい。専門的には「テレメトリ(遠隔測定法)」と言ったりするのですが、例えばゲーム発売後、ユーザー全体の統計情報を求めることもあります。特にソーシャルゲームはユーザーの離脱を抑えるため、そうした統計分析が行われ、サービス向上につとめています。こういった流れは、ソーシャルゲーム以外にも広まりつつあります。

鈴木:お話を伺っていると、現実の世界よりもゲームのほうがデータの活用が進んでいるように感じます。ゲームにおけるデータ活用はどのように進んでいったのでしょう?
三宅:先進的な事例では、ユーザーの生体データを取り、ゲームにフィードバックする、という事例があります。
ブレイクスルーのきっかけになったのは、海外でリリースされた『カウンターストライク』というネット対戦型FPS(ファースト・パーソン・シューティングゲーム)でした。これは世界的に大ヒットしています。
当初、開発者たちはなぜこのゲームがヒットしたのかわからなかったそうです。しかし偶然にも「戦闘状態と敵が退いている状態の時間バランスが非常にうまくできている」ことに気づいた開発者たちは、それがヒットの要因だと仮説を立て、新たに緩急を意識したゲームとして『Left 4 Dead』というゾンビゲームを世に送り出しました。こちらも大ヒットしています。
さらにこのときはテストプレイ時にプレイヤーの緊張度を測定し、それをゲームにフィードバックしたといいます。まだまだ不完全な部分はありますが、生体デバイスとの連携などもまだ発展の余地があると領域だと思います。
鈴木:現象を観察し、仮説を立てて実行し、結果を検証するというプロセスですね。「直感」を検証できるようになった背景にはデータの存在が欠かせません。体験のデザインといった直感的なことを扱うにあたり、仮説を立て、その検証に必要なデータを定義し、データの項目が妥当かどうかを確かめるというアプローチで、まさに我々も試行錯誤しているところです。

ゲームAIとは何か
鈴木:三宅さんの著書『人工知能の作り方』を拝読しましたが、ゲームAIには「メタAI」と「キャラクターAI」と「ナビゲーションAI」というものがあるそうですね。著書によると、メタAIは「ゲーム全体を監督する」。キャラクターAIは「ゲームに出てくる敵や味方、NPC(街で話しかける人などプレイヤー以外のキャラクター)の頭脳」、ナビゲーションAIはゲームの地形にキャラクターAIやメタAIが適応できるように合わせる役割……。この役割分担について、もう少し詳しく教えていただけますか。
三宅:ゲームのなかで「ユーザーが操作する主人公」以外のキャラクターはいわば“脇役”です。そして彼ら役者たちをゲーム内で“自律的な存在”に育て上げるのがキャラクターAI。しかし自律性を持ったキャラクターはゲームの中で勝手に動き回りますから、そのままではゲーム全体にまとまりがでません。そこで、メタAIが監督として役者であるキャラクターたちの自律性を抑えながら彼らの役割を制御し、プレイヤーにとってのゲーム体験を俯瞰的にデザインしているという関係性です。



メタAI、キャラクターAI、ナビゲーションAIの3つが連携してユーザー体験を作り出す。今回は特にメタAIとキャラクターAIにフォーカスしてお話をうかがった(三宅陽一郎『人工知能』(技術評論社)を参考に編集部にて作成)
鈴木:なるほど、そんな風に役割分担が行われているんですね。私たちがこの考え方をAFFECTIVE DESIGNのプロジェクトに応用しようとしたときには、メタAIによる「俯瞰的な体験のデザイン」が特に重要だと思いました。メタAIの役割について具体的に教えていただけますか。
三宅:わかりました。RPGを例にすると、かつてのゲーム開発で「レベルデザイン」と言われていた工程では、ダンジョンのかたちとともに敵の配置が厳密に決められていました。この場合、あらかじめすべてがお化け屋敷のように“決まっている”ので、誰が何回やってもプレイヤーにとって同じダンジョンになります。
鈴木:それがゲームに飽きがくる原因にもなっていたんでしょうか?
三宅:その可能性が高いかもしれません。そして、オープンワールド型のゲームが発展していくのに伴って、「監督役のAIがゲーム全般をコントロールする」という発想が生まれました。イメージとしては「キャスティングされた敵キャラクターを裏で待機させ、進行ルートの予測など(プレイヤーの)動きに合わせ、適切なタイミングと場所で敵が出現する」といった感じです。その実現のため、メタAIがユーザーのデータに合わせて、個人個人、その場その場の戦闘のバランスを調整しています。

メタAIはプレイヤーの
心理を読み取る?
鈴木:ゲームバランスを左右するメタAIは、「体験のデザイン」を司るという意味で、我々のようなリアルなサービスをつくるデザイナーと三宅さんたちゲームデザイナーとの接点になるのではないか、と感じています。
例えばAFFECTIVE DESIGN PROJECTがお手伝いをしたEQ HOUSEという事例は、家のなかで暮らす人と“家そのもの”がコミュニケーションをとり、空間をパーソナライズしていく未来を描くプロジェクトです。個人の体験を作るうえで、ゲームAIと同様に、何をデータとして取得し、家のなかで暮らす人に何をフィードバックするかがポイントになります。その設計では、家具や家電など一種の“キャラクター”が建築物のなかにいるユーザーに働きかけて、環境を最適化し俯瞰する、そんなメタAIに近い視点で発想していたように思います。
そういった文脈でお伺いしたいのですが、三宅さんがメタAIでゲームを演出していくうえで大事にしている着眼点はどんなところでしょうか。
三宅:前提として、ゲームデザインではユーザーの心理を意図した方向に誘導したいという思いが裏側にあります。例えば、敵に囲まれたら焦ってもらいたい。きっと逃げ出したいだろうから、意図的に逃げ道を用意しておき、そちらに誘導する。でもそこにはもっと恐ろしいモンスターが出現して……というように。
メタAIの大目的は “プレイヤーの心理”を読み取ってユニークな体験をもたらすことです。実際に心理を誘導できているかを確かめるためのデータを取得して開発に活かすこともあります。
鈴木:どうやってデータを取っているのでしょうか。
三宅:もちろん心理そのものは数字で取れないので、時間あたりの敵討伐数、受けたダメージ、ダメージの減り方等々のアクションを指標としながら、こちらが想定する心理の動きと合致しているのかを追跡します。追跡結果を検証して、ゲームのデフォルト設定からゲームバランスを調整していくようなやり方です。

ゲームAI開発者による
“自然さ”の作り方
鈴木:ここまでがメタAI寄りのお話だとすると、ここからはキャラクターAI寄りのお話をさせてください。お伺いしたいのはゲーム内の役者であるキャラクターがまとう“自然さ”について。三宅さんは人やモンスターの立ち振る舞いをゲーム内で表現・演出されていますよね。突き詰めれば“自然さ”とは何かという問いかけに通じますが、それらをどのように観察し、ゲーム開発に活かされているのでしょうか。
三宅:こちらについても、もう少し前段からお話しさせてください。ゲームAIの特徴を挙げるとすると「リアルタイム」「インタラクティブ」「身体(体を持っている)」の3点です。
同種の特徴をもつAIはロボット以外にほとんどなく、ゲームキャラクターをつくるというのはロボットをつくる行為にも近い。しかし他方で、人間もまた「リアルタイム」「インタラクティブ」「身体」を持つ存在なので、特にゲーム内の人間のキャラクターが実際の人間からズレた行動をとってしまうと、ユーザーから厳しい目で見られたりもします。
鈴木:モンスターだとわりと寛容に見られるということでしょうか? 実際に存在しないものをデザインするという意味では、人間のキャラクターとは別の難しさもありそうです。
三宅:そうですね、モンスターについてはある程度の不自然さなら目を瞑ってくれると思います。ただモンスターは実際には存在しないがゆえに、頭のなかだけで考えると、どうしてもロジカルな、どこか乾いた存在に仕上がってしまいますね。
モンスターを担当する開発者は、山、洞窟、サファリパーク、猿山……などさまざまな場所に赴き、実際の動物の動き・しぐさからリファレンスを得ることもあります。一方、人物の場合も、新宿のような大勢の集まる街に行き、群衆というものがどういう動きをするのか、観察してその特徴を抽出しますし、心理学などの論文を読むなどもしています。

鈴木:観察ベースと理論ベースの両方からリサーチをされているんですね。
三宅:もう少し付け加えると、真面目にキャラクターを作り過ぎるとどうしても合理的な意思決定ばかりになって失敗することが多いですね。人間はある程度不合理な存在なので、少し“愚か”なくらいがちょうどいい。キャラクターの動作にも、余白をもたせるためにポリポリと頭を掻いたり、ゆらゆら頭が揺れていたり、無意識的な行動を取り入れます。
鈴木:無意識的な行動ですか。おもしろいですね。以前、劇作家・演出家の平田オリザ氏が「上手な役者と下手な役者の違いは、“無駄な動き”にある」と話されている文章を読んだことがあります。そこで語られていた、無駄だけど自然な動作といった、無意識の領域をいかに残すかという話にも通じるように感じます。
三宅:おっしゃるとおり、自然さのためにあえて不合理を取り入れることは重要です。あとは、キャラクターAIではそれぞれのキャラクターごとに知能をカスタマイズできるようにしています。例えばあるキャラはとても深い思考をするため予測に長い時間を充てるし、別のキャラは浅い思考のため短絡的行動をたびたびする。レスポンスの反応もさまざま。モンスターも大きいものは動きが遅いし、小さいものは素早い……。
実際の社会でも友人たちと一緒にいるときに、みんな同じタイミングで一斉にこっちを振り向いたらちょっと不気味じゃないですか。それと同じで、ゲームキャラクターにも多様性が必要です。そういった要素によって、全体として自然さを演出できると思います。
キャラクターの自然な振る舞いはAIによって演出されている
鈴木:なるほど。実際の社会で不自然なことはゲームの中でも変わらないのですね。ゲームの内容は時代とともに複雑さを増していると思うのですが、ゲーム開発のチーム体制はどのようになっているのでしょうか。
三宅:まずは自らの体験をベースに担当者がそれぞれ試作品を作ります。その後は定期的にチェックするタイミングを決めておいて、そこにデザイナーもプログラマーも一斉に集まり、立場に関係なく、気づいた点を話し合います。それを次のミーティングまでに改善し、再びみんなでチェックする。そんなサイクルを繰り返していますね。
鈴木:試作品づくりは必ず行っているのですか。
三宅:もちろんタイトルにもよりますが、リアリティを求めるキャラクターの作成には、「リアルな体験からゲームを作る」ことが一つの前提となります。映画やアニメ、これまでのゲームをリファレンスにすることもありますが、ともすればゲームからゲームを作ると内容が薄まっていきますから、体験をベースにした試作品づくりは非常に大事だと考えています。
鈴木:体験のデザインにまつわる話題として、とても新鮮なお話でした。観測がベースになっているというのはデザイナーによるフィールドワークにも似ていますし、お伺いした理論は「人間の本質を理解する」うえで、我々もおさえておきたいポイントだと感じます。

メタAIを現実空間に
応用していきたい
鈴木:改めてお伺いしますが、三宅さんがユーザーの心を動かすうえで、大事だと考えているのはどんな点ですか。
三宅:ゲームは基本的にエンターテイメントですから、のめり込んでもらうためには、いい意味で、ユーザーの日常の心のバランスを崩すような設計と、崩した瞬間に「こっちだよ」と誘導するような動線の両方が必要だと思います。RPGにしても強いモンスターが出てきて、あと一息でやられそう……ってときに味方のキャラクターが手助けしてくれたら、心を開きますよね。味方のキャラクターはAIですが、ピンチの瞬間に助けてもらうと途端にAIへ親しみが湧くようになります。
鈴木:家庭用のロボットなどにも通じるお話ですね。
三宅:実は家庭用ロボットがしんどいのはそのあたりで、均衡の取れた日常生活では、ロボットを受け入れる心の隙がなく、感情移入がしにくいはずです。ストーリーがないと文脈も作れないので、ただそこにいるだけの存在になってしまいがちです。難しい問題ですね。そういう意味では、ロボットに対してもある程度のストーリーをデザインしてあげるのもいいかもしれない。月を一緒に見たがるお掃除ロボットがいても面白いですよね。
鈴木:それは素敵ですね。
三宅:もう1つ考えているのは、AIの制御をユーザーにどの程度意識させるべきかという話です。必ずしも、AIの全てを制御できるようにするのがいいというわけではありません。あくまで知能と環境とのインタラクションが重要になるので、理想の状態はユーザーが「無意識にAIを制御できる」ことかもしれません。ただ、ユーザーのなかには「すべてを自分で細かく制御したい」という人もいるので、一概には言えないのですが。
鈴木:その「意識と無意識の境界線を調整する」ところはまさしくAFFECTIVE DESIGNが注力しているところです。ユーザーが何をコントロールしたいと思っているのかを掴み、それをどうコントロールするべきかをメタAIが制御するというかたちが実現すると面白いですね。今後、ゲームAI開発者として三宅さんが考えていることはありますか。
三宅:メタAIを現実空間に応用していきたいと考えています。2019年12月、スクウェア・エニックスはオムロン社と「人のモチベーションを高めるAI」の共同研究についてのリリースを出しましたが、このようなメタAIとの協調によって現実社会の体験をデザインしていく試みは徐々に増えていくと思います。ただメタAIはまだ発展途上で、開発しながら、その品質と可能性を同時に発見している最中です。その時々のユースケースに合わせながら発展させていくことが、メタAIの可能性を広げていくのだと思います。
鈴木:具体的に、メタAIのどのあたりに発展の余地があるとお考えでしょうか?
三宅:メタAIの最終的な目標は人間を理解して、コンテンツを展開することです。しかし、現在は、限定された場にしかメタAIを働かせられていないというところでしょうか。今後は、SNSなどでユーザーの人となりを把握したうえでパーソナライズしていくという方向に進化していくかもしれません。メタAIは、人と技術の間に立って、技術を調整する役割を持つようになります。
鈴木:応用先としてはどのようなものを思い描いていますか。
三宅:スマートシティにしてもそうですし、先ほどの鈴木さんのお話にもあったようなスマートハウス的発想にも応用できそうですよね。家具・家電など、個々のエージェントとしてのAIと協調しながら、メタAIが家全体を制御していく。そんなことも可能になると思います。
鈴木:現実世界における現状のAIはそれこそキャラクターAI的な、個々のエージェント的な発想でつくられたものがほとんどだと思います。そんななか、環境全体を制御するために重要になるのはメタAI的な発想だと感じました。我々、AFFECTIVE DESIGN PROJECTでもメタAI的な発想をもって、環境と協調し人に自然に寄り添うリアルなサービスをつくって行きたいと考えています。本日はありがとうございました。
三宅:ありがとうございました。
(取材・文:安田博勇、撮影:平郡 政宏[カウンタック写真部])